
実は私も学習していた時は、本当にリスニング(听力)が苦手でした。音声データで繰り返し繰り返し聞いているのに、同じ内容の会話が聞き取れない。知っているはずの単語を聞いてもわからない。そういった経験はそれこそ山のようにありました。
当時の私は、「聞き取れないのは、中国語特有の発音が聞き分けられないから」と母音や子音、声調を見直してみたりもしました。耳が悪いんだと思ったんですね。私だけでなく、多くの学習者が同じように感じているようです。
でも、今なら分かりますが、それは違っていました。
耳が良い人って世の中にはいますので、そういう人たちにとっては語学は非常に有利であることは間違いないです。でも、一方で聞き取りが出来ない原因は耳ではなく別のところにあることが分かりました。
聞き取れるかどうかは、脳内変換できるかどうか
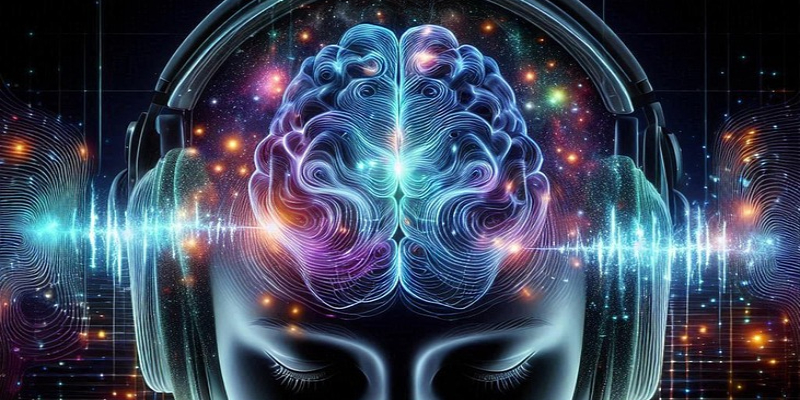
これ、中国語ではなく、日本語で考えると良くわかります。
私たちが脳内で無意識にやっていることをこれから実証します。以下のひらがなの文章を読んでみて下さい。
みなさん、こんちには。きょうの じけっんは だいせうこうだ。まさか こんなめちゃくちゃな ぶしょんうが ふつうによめてましうなんて。
にんげんの のうは あんがい いいげかんで じゅうなんいせも あるんだな。はなしてるいことばも じつは こんなふうに むしいきに ほせいをかてけいるんだ。
どうですか?多少違和感はあるものの、内容は読めたりしませんでしたか?
これはタイポグリセミアという現象らしいのですが、言いたいことはこの現象の解説ではなくて、私たちは無意識に脳内で補正をかけているということです。ちゃんとした文章でなくても、その意図が伝わるようになっています。
そして、これに似た現象が会話でも行われています。
騒音の中でも会話ができるのはなぜ

例えば地下鉄とか交差点とか、意外とうるさいところでも私たちは会話しています。もちろん工事現場のすぐ横とかで、ほぼ聞こえない状態では無理なことですが、多少部分的に聞き取れなかったことがあったとしても会話が出来ています。私たちの脳は、もともと多少の虫食いがあってもコミュニケーションとれるのです。
これは聞き取れなかった音に対して、脳が話の前後関係や相手の表情、相手が言いそうなことの想定を予測して補完して、全体の意味を理解しようとします。先ほどのタイポグリセミアを耳で行なっているようなイメージです。(※厳密には違いますが、分かりやすい例として。)
あと、関東の人と関西の人が会話する際、お互いに理解し合えるのは、違った発音・言い方だけれども意味は同じという脳内のDB(データベース)があるお陰です。反対に、津軽弁や馴染みのない方言であった場合、脳内DBがないわけですから、聞いたとしても「?」ってなってしまいます。そういった経験ありますよね?
中国語でも同じことが起こっている
中国語をちゃんと聞き取ったのに、意味が分からないという場合、音声からのアクセスで脳内で検索が出来ていないことになります。音とその意味を紐づけるネットワークがないと、仮に聞き取れたとしても意味を構築することができません。
これが、「文字で見れば分かるのに、聞いても分からない」現象の正体です。目から(文字から)のアプローチはたくさんしていますが、耳からのアプローチが少ないがために、意味を拾う際に虫食い状態が穴だらけで全く分からなくなります。
裏を返せば、ある程度推測が出来る状態であれば、多少聞き逃したり、聞こえなかったりしても、脳が前後関係から補完するため意味が取れたりします。私も過去にたくさん経験しましたが、おおよそ予想できる状況下で会話すると思いのほか分かったりするものです。また、実際に対面して会話をする場合、耳以外でも相手の表情やジェスチャーから得られる情報もたくさんあり、より多くの補完が可能となります。
ではどのように学習するのが正解なのか
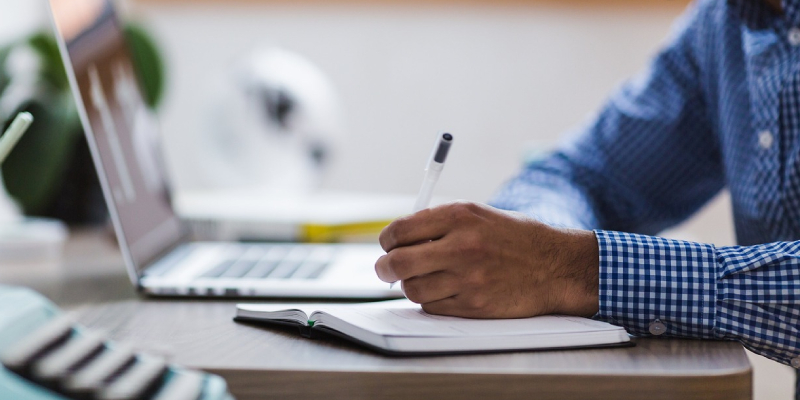
原因は、聞こえた音とその意味とのネットワークがないからです。で、あれば、そのネットワークを構築することが肝心となります。多くの(特に日本人)学習者は、ピンイン表記で文章や単語の読み方を確認しますが、そのネットワークが薄い人はだいたい黙読しています。頭の中で読み方と意味を繋げているように見えますが、実際に音をセットにしないといけません。
つまり、
毎回必ず発声してみる
付属の音声を何回も聞く
シャドーイングしてみる
これに尽きます。なんだ当たり前じゃないかと言うかもしれませんが、意外とちゃんとやっていない人が結構います。やっているよ、っていう人に「何回くらい?」と聞くと5~10回というような回答いただきます。…申し訳ないですが、少なすぎます。その10倍はやるべきです。
一方で、漫然と数をこなすのも考え物です。目的は、音と文字と意味を紐づけること。中国語を聞いたら必ず意味を捉える、自分でも発音する癖をつけます。無意識に、反射的に、口をついて出てくるように繰り返します。
こういう形で中国語のDBを増やしていくと、聞いて分かる中国語がどんどん増えていきます。
具体的にどうやっていくのかは、コーチングで指導させていただいています。おかげさまで皆さん段々と聞けるようになっています。引き続き頑張っていきましょう。
